※記事内に広告を含みます。
今まで植物をあまり買ったことがなくて、観葉植物を育て始めると
- 病害虫が発生するの?
- 病害虫ってそもそもなに?
などの疑問が出てくると思います。そして、わからないし虫なんか嫌い!!とあわてるひともいるのではないでしょうか。
そんなあなたのために、園芸初心者にもわかりやすくインテリアグリーンの病害虫対策についてまとめました(^^♪
コバエは気を付けないと発生します!
水やりしたときに、受け皿にあふれる水はきちんと捨てないとコバエが発生します。1回1回きちんと受け皿の水を捨てましょう。
観葉植物の病害虫対策で普段チェックすべきこと☆早期発見が大事
実は、そんなに心配しなくても観葉植物は花や野菜に比べると病害虫による被害は少ないです。

とは言っても
- 買う前に植物自体や土に害虫の卵や病原菌が潜んでいる
- 窓から風といっしょに害虫が運ばれてくる
こともあります。また、鉢土が乾燥し過ぎていたり、過湿、葉が増えてギュウギュウになりすぎても病害虫が発生する原因になります。

- 植物に適した置き場所
- 植物に合う土
- 適した水やり
- 適した肥料の量
などを守ると、病害虫の発生を抑えることができます。
植物や鉢土の清潔さもポイントです。
月に1回ほどホコリや汚れを洗い流してあげるといいです。枯れ葉やごみがあったら取り除き、フォーク等で土の表面を少し耕してあげましょう。
害虫は見えにくい場所にいるので、葉っぱの裏や新芽、株元などを観察しましょう。
観葉植物に発生しやすい病害虫は
- アブラムシ
- カイガラムシ
で、これらの病害虫は発生初期の段階ならティッシュや湿らせた綿棒でこすり落とせます。株元に落としたままだと、また植物についてしまうので見つけたものは確実に捕殺せよ・・・と大体の園芸書には書いています。要するに殺せってことで指でつぶす猛者もいるようですが、なかなかハードルが高いので
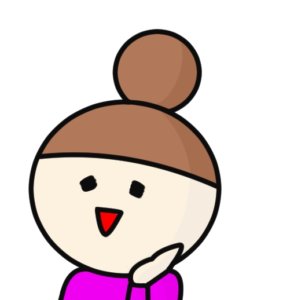
病害虫はマリーゴールドの香りが嫌いなので、マリーゴールドをそばに置くのもおすすめです。
観葉植物に発生しやすい害虫
| アブラムシ | 若い新芽について汁を吸うと植物が弱ってすす病の発生原因になる。 |
|---|---|
| カイガラムシ | 枝や葉について汁を吸って植物を弱らせ、すす病の発生原因にもなる。葉や茎が排泄物でべたついて黒く汚れてしまう。 |
| ハダニ | 大きさは0.5㎜ほどで葉裏について汁を吸うと、葉が白くかすり状になります。乾燥状態だとたくさん発生して多湿を嫌うので葉水で予防できる。生育不良を引き起こす。 |
| ナメクジ | 室内だとあまり発生しない。夜になると活動して新芽を食べてしまう。這ったあとが光る。見つけたらすぐに取り除く。 |
【使い方】病気が発生したら殺菌剤、害虫が発生したら殺虫剤を
薬剤はそれぞれ効果がある病気や害虫が決まっているので、適さないものを使うとなんの効果もありません。どんな病気なのか、どんな害虫がいるのかをしっかり確認してから薬剤を選びましょう。
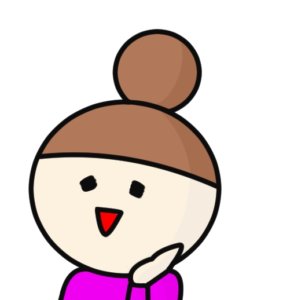
薬剤は使用法をよく確認して使いましょう。
薬剤を使える時間帯がある
薬剤を使う時間帯は昼の気温が高い時ではなく、朝や夕方の少し涼しい時間帯、または曇った日にしましょう。
晴れた日の日中に薬剤をまくと、薬害が出やすいので気をつけます。
薬剤を使う時は必ず装備をする
マスク・手袋は必須。メガネや帽子も用意しましょう。
薬剤を使う場所
室内に置いてある観葉植物に薬剤を使うときは、いったん外に出して屋外で薬剤を使いましょう。
薬剤の使用後は
せっけんで手や顔を洗います。使った器具もキレイに洗浄します。
病気・害虫別に使える薬剤を紹介します
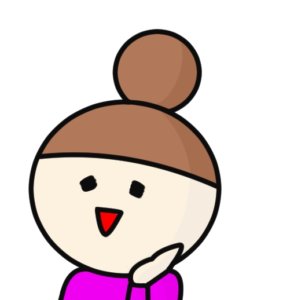
そんなあなたのために、それぞれに使える薬剤を紹介していきます。
炭疽病に使える薬剤
炭疽病は、炭疽病菌が原因で葉っぱの表面に円形や楕円形の斑模様ができてその部分が枯れてしまう病気です。
斑点病に使える薬剤
斑点病は、葉の表面に褐色の斑点の病斑がつく病気です。
灰色かび病に使える薬剤
灰色かび病は、葉っぱや茎に灰をかけたようなカビができる病気です。
うどんこ病に使える薬剤
うどんこ病は、葉っぱが粉をふったように白くなる病気です。
アブラムシに使える薬剤
カイガラムシに使える薬剤
ハダニに使える薬剤
ナメクジに使える薬剤
ナメトールは天然成分で、犬や猫を飼っているご家庭でも使えて安心。
家庭菜園にも使えます☆
まとめ
害虫や病気に応じてそれぞれ使う薬剤が違うので、しっかり確認して使うようにしましょう。
日々、観葉植物をしっかりケアしていれば病害虫の被害にあう可能性はグッと下がります。
あまり神経質になる必要はありませんが、気を付けてみてください。
\最後にポチってもらえると飛んで喜びます☆/










